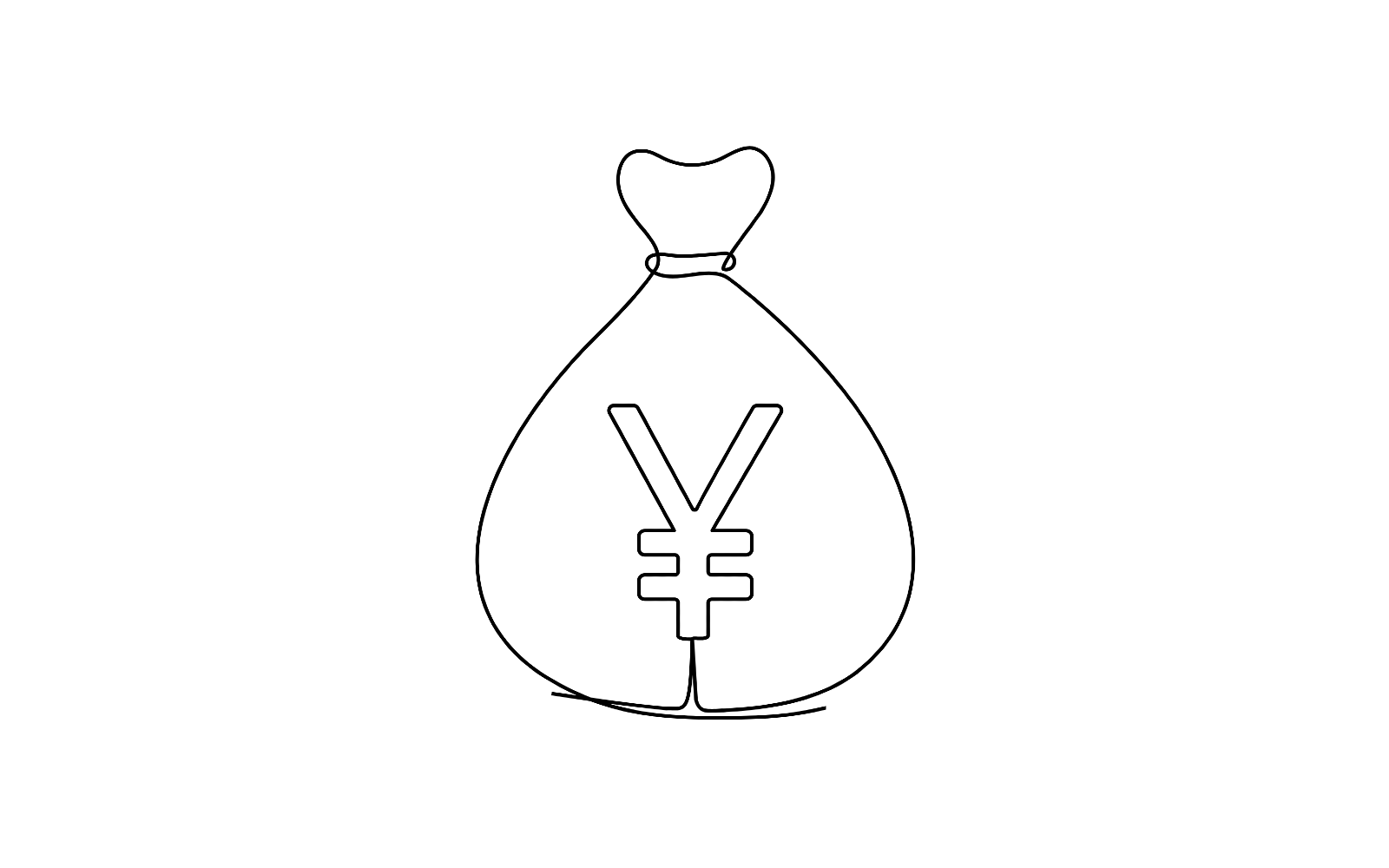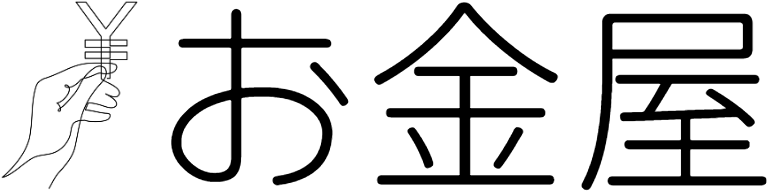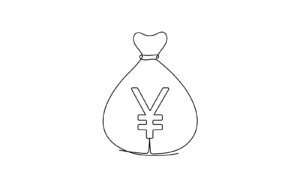こんにちは、お金屋です。
先日、実家に帰省した際、近所のおばさんから「まだ家を買わないの?賃貸はお金を捨ててるのよ」と言われました。日本では昔から「いずれはマイホームを」という価値観が強いですよね。でも、本当にそうなのでしょうか?
実は私、これまでの人生で「賃貸マンション」「実家暮らし」「持ち家(マンション)」「持ち家(一戸建て)」と、様々な住まい方を経験してきました。そして今また、都心の賃貸マンションに住んでいます。
「お金の面から見た住まいの選択」というテーマは、人生で最も大きな金銭的決断の一つです。今日は、私自身の経験と数字に基づいて、「マイホーム神話」の真実について考えてみたいと思います。
「家賃は捨てるお金」という誤解
「家賃は捨てるお金、ローンは資産になる」というフレーズ、よく聞きますよね。でも、この考え方には大きな落とし穴があります。
私が最初に購入したのは、都内の中古マンション。当時はまさに「家賃を払い続けるなら、同じ金額を払って自分の資産にした方がいい」と考えていました。
ところが、数年後に転勤が決まり、そのマンションを売却することに。そこで初めて気づいたのは、「住宅ローンの返済額」と「資産として残る金額」には大きな差があるという現実でした。
例えば、3,500万円のマンションを購入し、頭金500万円、金利1%の35年ローンを組んだ場合:
- 総返済額は約4,100万円(元本3,000万円+利息約1,100万円)
- 5年後に売却した場合、減価償却や市場変動で約3,200万円に
- 売却時の諸経費(仲介手数料など)で約160万円
結局、5年間で支払った約590万円のうち、資産として残ったのは約200万円弱。差額の約400万円近くは、金利や手数料、価値減少として「消えた」お金だったのです。
つまり、「ローンは全額が資産になる」わけではなく、かなりの部分が家賃と同様に「消費」されているのが現実です。
「持ち家 vs 賃貸」の本当の比較方法
では、どちらが得なのか?単純に「月々のローン返済額」と「家賃」を比べるのではなく、総合的なコストで考える必要があります。
私の経験から導き出した比較方法はこうです:
持ち家のコスト
- ローン返済額(元本+金利)
- 固定資産税・都市計画税
- 修繕積立金(マンションの場合)
- メンテナンス費用
- 火災保険料
- 【マイナス】資産価値として残る部分
賃貸のコスト
- 家賃
- 更新料・礼金
- 【プラス】持ち家との差額を投資に回した場合の運用益
例えば、同じエリアの似た条件の物件で試算してみると:
【持ち家(3,500万円のマンション)の場合】
- 月々のローン返済:94,000円
- 固定資産税など:月換算 約8,000円
- 修繕積立金:15,000円
- 一般修繕費用:月換算 約5,000円
- 火災保険:月換算 約2,000円
- 合計:124,000円/月
【賃貸(同等物件)の場合】
- 家賃:100,000円
- 更新料等:月換算 約3,000円
- 合計:103,000円/月
この比較だけを見ると、月々約2万円の差があります。しかし、その差額を投資に回したり、キャリアの柔軟性を保つことによる収入増の可能性を考えると、必ずしも持ち家が経済的に有利とは言い切れないことがわかります。
人生のステージで変わる「最適解」
住まいの選択に「絶対的な正解」はありません。私の経験から言うと、「ライフステージによって最適解は変わる」という視点が重要です。
20代〜30代前半:キャリア構築期
この時期は転職や転勤の可能性が高く、自由度を保つ賃貸に大きなメリットがあります。私も30代前半で海外駐在の機会をもらい、2年間の予定で引っ越しました。持ち家があったら、この貴重なキャリアチャンスを逃していたかもしれません。
30代後半〜40代:家庭安定期
子育て世代になると、学区や住環境を重視する傾向があります。また、キャリアも安定し、住み続ける期間が長くなる見込みがあれば、持ち家のメリットが大きくなります。私も38歳で一戸建てを購入し、子どもの教育環境を重視しました。
50代〜:ダウンサイジング検討期
子どもの独立や老後の生活を見据え、大きな家から適切なサイズの住まいへの転換を考える時期。私の両親も子ども達が巣立った後、広すぎる一戸建てから便利な駅近マンションへ引っ越し、生活の質が上がったと喜んでいます。
重要なのは、「持ち家 vs 賃貸」という二項対立ではなく、「今の自分のステージにはどちらが適しているか」という視点です。
見落としがちな「持ち家のメリット・デメリット」
住まいの選択は単純な損得だけでは測れません。持ち家と賃貸のより深いメリット・デメリットを考えてみましょう。
持ち家の隠れたメリット
- 自由なカスタマイズ:壁を塗り替えたり、設備を変更したり、自分好みの空間づくりができる。これは意外と大きな生活の質向上につながります。
- 心理的な安定感:「自分の城」という安心感は数値化できませんが、実際に私も持ち家に住んでいた時は「ここが終の棲家」という安堵感がありました。
- 資産防衛効果:インフレに強いという特性があります。実際、私の両親が30年前に購入した家は、名目価値はほぼ変わらず、家賃が2倍近くになった地域でその恩恵を受けています。
持ち家の隠れたデメリット
- 機会コストの大きさ:住宅購入に大きな資金を投じることで、他の投資機会を逃す可能性があります。
- 流動性の低さ:急な転職や家族構成の変化に対応しづらく、キャリアの選択肢を狭める可能性も。
- 維持管理の精神的負担:エアコンの故障や屋根の雨漏りなど、予期せぬトラブルへの対応は家主の責任。これは意外と大きな精神的ストレスになることがあります。
特に印象的だったのは、持ち家に住んでいた時の「修繕・メンテナンスへの意識の変化」です。賃貸では気にならなかった「この先10年、20年」という長期的な視点で、家のことを考えるようになりました。
住まいにまつわる「お金の真実」3つ
私の経験から学んだ「住まいとお金」に関する真実をお伝えします。
真実1:「立地」は投資、「広さ」は消費
不動産の価値で経年劣化しにくいのは「立地」です。一方、「広さ」や「設備のグレード」は時間とともに価値が下がりやすい傾向があります。
私が最初に購入したマンションは「駅から遠いけど広い」物件でしたが、売却時に苦労しました。一方、2軒目に購入した「駅近だけどコンパクト」な物件は、売却時に購入価格とほぼ同額で売れました。
資産価値を重視するなら、「無理に広さを求めず、良い立地を選ぶ」方が賢明だと実感しています。
真実2:住宅ローンは「強制貯金」の側面を持つ
住宅ローンの返済は一見大変ですが、「強制的に資産形成できる」という側面があります。賃貸で節約した差額を本当に投資に回せるか、自分の性格を正直に見つめる必要があります。
私の場合、賃貸時代は「差額を投資に回す」と決めていたものの、実際には使ってしまうことも多かった。一方、持ち家時代は嫌でも毎月のローン返済があり、結果として一定の資産形成につながりました。
自分の消費傾向に正直になり、「強制力」が必要かどうかを考えることも大切です。
真実3:「住む」ことと「投資」することは分けて考える
「住まい=投資」と考えると、しばしば居住性を犠牲にした選択をしがちです。しかし、住まいの第一の目的は「快適に暮らすこと」であり、投資対象としては他にも選択肢があります。
私は現在、「住むこと」と「投資すること」を分離する選択をしています。具体的には、住まいは利便性を重視した賃貸を選び、その分の資金を不動産投資信託(REIT)や株式などに分散投資しています。こうすることで、住環境の自由度を保ちながら、不動産市場の成長も享受できるバランスが取れています。
持ち家と賃貸、選ぶ際のチェックリスト
最後に、住まいを選ぶ際に考慮すべきポイントをまとめました。
持ち家を選ぶべき状況
- 最低5年以上、できれば10年以上住む予定がある
- 家族構成が安定している(急な変化が予想されない)
- 職業や勤務地が安定している
- DIYや家のカスタマイズを楽しみたい
- 資産形成のための「強制力」が欲しい
- インフレへの備えとして実物資産を持ちたい
賃貸を選ぶべき状況
- キャリアの変化が予想される(転職、転勤の可能性)
- 数年以内に家族構成の変化が予想される
- 住環境よりも利便性や職場への近さを優先したい
- 資産運用を分散して行いたい
- 住まいの維持管理に時間を取られたくない
- 将来の引越しの自由度を確保しておきたい
このチェックリストを見ると、私が現在賃貸を選んでいる理由も明確です。仕事の関係で都心に住む必要が出てきた今、「資産としての家」より「生活の質を高める住まい」を優先した結果なのです。
まとめ:「住まいのお金」を考える新しい視点
「持ち家 vs 賃貸」という古典的な対立軸から一歩進んで、「自分のライフステージと価値観に合った選択」という視点で考えることが大切です。
私の経験から言えることは:
- 持ち家も賃貸も、それぞれの「見えないコスト」を理解する
- 単純な月々の支払い比較ではなく、総合的なコストで判断する
- ライフステージによって最適解は変わるという柔軟性を持つ
- 「住むこと」と「投資すること」は必ずしも同じ選択にしなくてもいい
- 自分の価値観に正直になり、「見栄」ではなく「幸福度」で選ぶ
「マイホーム神話」に惑わされず、冷静に自分の状況を分析し、最適な選択をすることが、真の「住まいの幸福度」につながると信じています。
住まいは単なる「箱」ではなく、人生の質を大きく左右する重要な要素。経済合理性だけでなく、「自分らしく生きるための拠点」という視点も大切にしたいですね。
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。皆さんの「住まいの選択」が、経済的にも心理的にも満足のいくものになりますように。
また次回のブログでお会いしましょう!
お金屋より