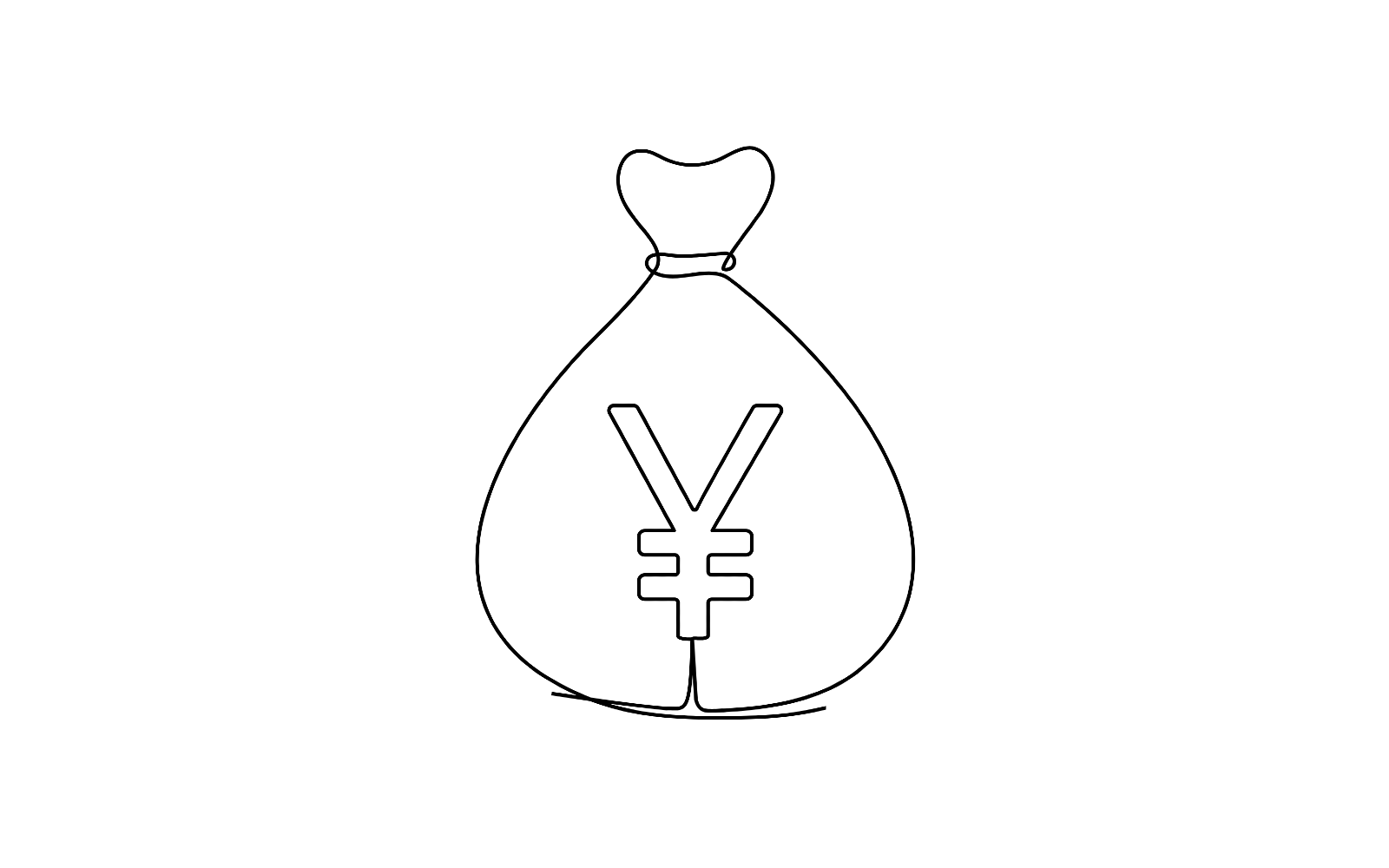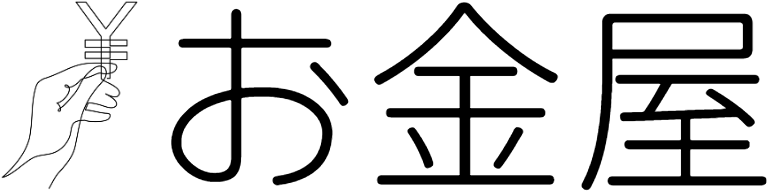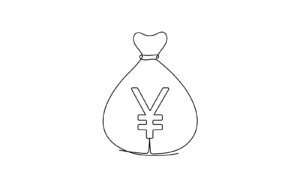こんにちは、お金屋です。
先週末、久しぶりに高校時代の友人と再会しました。彼女は今、心理学の研究者として大学で教鞭をとっています。久しぶりの再会で話に花が咲き、気づけば居酒屋で3時間も経っていました。お会計のとき、彼女が「これは幸せな時間のお金だから、惜しくないね」とニッコリ。この一言が妙に印象に残り、帰宅してから色々と考えさせられました。
私はこのブログでよく「賢い節約術」や「資産形成のコツ」について書いてきましたが、今日は少し視点を変えて「お金の使い方」について考えてみたいと思います。
というのも、友人との会話の中で「お金と幸福度の心理学」という彼女の研究テーマを聞いて、目から鱗が落ちる発見がたくさんあったんです。「お金を貯めることも大事だけど、使い方も同じくらい大事なのよ」という彼女の言葉が、今も心に残っています。
お金で幸せは買えるのか?〜心理学研究の意外な結論〜
「お金で幸せは買えない」という言葉、よく聞きますよね。でも、友人によると、最新の心理学研究では「お金で幸せは買える。ただし、使い方によって幸福度が大きく変わる」という結論になっているそうです。
例えば、2010年代に行われた研究では、年収が上がると幸福度も上がるという結果が出ています。ただし、それには上限があり、基本的な生活が安定してからの収入増加は、幸福度への影響が小さくなるんだとか。
また、「モノへの支出」と「経験への支出」を比較した研究では、一般的に「経験にお金を使った方が、長期的な満足度が高い」という結果になっています。
つまり「お金の額」よりも「使い方」こそが、幸福度を左右するポイントなんですね。
「幸せなお金の使い方」5つの法則
友人が教えてくれた「幸せを最大化するお金の使い方」を、5つの法則にまとめてみました。
法則1:「モノ」より「経験」にお金を使う
心理学研究によると、新しい服やガジェットを買ったときの喜びは比較的短期間で薄れていきますが、旅行や習い事などの経験は、時間が経っても温かい思い出として残り、むしろ美化されて幸福感が増すことがあるそうです。
友人が言うには「モノの価値は比較されやすく、慣れも早い。でも経験は唯一無二で、あなただけのものだから比較されにくい」とのこと。
私自身も振り返ってみると、高価なバッグを買ったときの興奮より、友人との温泉旅行の思い出の方が、今でも鮮明に幸せな気持ちを呼び起こします。
法則2:「将来の苦痛を減らす」ことにお金を使う
意外だったのは、「将来の苦痛を減らすためのお金の使い方は、幸福度を高める」という研究結果。
例えば、少し高くても家から近い物件を選ぶ、通勤時間が短くなる交通手段にお金をかける、家事の負担を減らす家電に投資するなど。日々の小さなストレスや不便を減らすためのお金の使い方は、長期的な幸福度に大きく影響するんだそうです。
友人の言葉を借りれば「1日10分の通勤時間短縮は、年間で40時間以上の自由時間を生み出す。それって新しいスマホを買うより価値があるかもしれないよね」。
この視点で考えると、少し高くても自宅の近くのスーパーで買い物をしたり、面倒な家事を減らすサービスにお金を使ったりすることは、実は「賢い投資」なのかもしれません。
法則3:「時間を買う」ようにお金を使う
現代人の多くが感じている「時間の貧困」。「やりたいことはたくさんあるのに、時間がない」という状態です。
友人によれば、「お金を使って時間を買う」という発想が、幸福度を高めるのに効果的だそうです。例えば、家事代行サービスを利用する、ちょっとした雑務を外注する、時間を節約できるサービスにお金を払うなど。
「でもそれって贅沢では?」と聞いたところ、友人は「時間は有限だけど、お金は稼ぎ直せる。だから自分の時間の価値を考えることは、実はとても賢明なことよ」と言っていました。
私も最近、食材の宅配サービスを始めましたが、買い物の時間が減って、その分好きな読書の時間が増えました。確かに幸福度は上がったかもしれません。
法則4:「今すぐ」ではなく「少し待ってから」楽しむ
心理学では「延期された満足感」という概念があるそうです。欲しいものをすぐに手に入れるより、少し待ってから手に入れる方が、喜びが大きくなる傾向があるんだとか。
友人によれば、「待つ時間」は「期待」という楽しみを生み出してくれるそうです。例えば、旅行を計画するとき、半年後の予約をして、その間に下調べをしたり、想像を膨らませたりする時間そのものが幸福感を高めてくれるんですね。
反対に、クレジットカードで衝動買いをして、後から「本当に必要だったかな?」と後悔するパターンは要注意。「欲しい」と思ったら、一度リストに書き留めて、1週間後に本当に必要か考え直してみる。これは賢いお金の使い方の基本だそうです。
法則5:「独りよがり」ではなく「つながり」にお金を使う
最も印象的だったのは、「人とのつながりを強化するお金の使い方は、幸福度を高める」という研究結果。
例えば、友人や家族へのちょっとしたプレゼント、一緒に過ごす時間のための支出(食事や活動など)、共通の趣味や関心事に関連する支出などが、長期的な幸福感につながるそうです。
友人の言葉で印象的だったのは「自分へのご褒美も大事だけど、大切な人との関係に投資することは、幸福度のリターンが高い投資なのよ」という言葉。
私自身、先日母の誕生日に少し奮発して素敵なディナーに招待したのですが、母が喜ぶ顔を見た幸せと、そのことを今でも感謝してくれる電話をもらうたび、「あのお金は本当に価値があった」と実感します。
「幸せな買い物」のための具体的な質問リスト
友人は、買い物をする前に自分に問いかける「5つの質問」も教えてくれました。大きな買い物をする前に、これらの質問に答えてみると、後悔しない選択ができるそうです。
- 「この買い物は5年後の私に何をもたらしてくれる?」 長期的な視点で見たとき、この支出が自分の人生にどんな影響を与えるか考えてみる。
- 「この買い物は誰かとの関係を深めてくれるか?」 人間関係の強化につながる支出かどうかを考える。
- 「この買い物で日常の小さなストレスが減るか?」 毎日の生活の質を高めてくれるかどうかを考える。
- 「この買い物は新しい経験や思い出を作ってくれるか?」 モノではなく、経験や思い出につながるかを考える。
- 「この買い物をしなかった場合、何に使えるか?」 機会費用を考えることで、本当の優先順位が見えてくる。
この質問リストを実践してみて、私が最近「YES」と答えられたのは、長年興味があった陶芸教室への入会費でした。新しい経験ができて、同じ趣味の友人もできそうで、将来的には手作りの器で家族をもてなせるかもしれない…と考えたら、迷わず投資する価値があると感じました。
「幸せなお金の使い方」を阻む3つの罠
心理学的に見ると、私たちはついつい「幸せではない方向」にお金を使ってしまう傾向があるそうです。友人が指摘してくれた3つの心理的な罠を紹介します。
罠1:「比較」の罠
私たちは自然と他人と比較してしまいます。「友達が持っているから」「SNSで人気だから」という理由での買い物は要注意。本当に自分が欲しいのか、単に人と比較して「持っていないと不安」と感じているだけなのか、見極めることが大切です。
罠2:「ステータス」の罠
心理学では「見栄消費」と呼ばれる現象があるそうです。自分の社会的地位や成功をアピールするための消費は、一時的な満足感をもたらしても、長期的な幸福にはつながりにくいとか。「誰かに見せるため」ではなく「自分の人生をより良くするため」の消費かどうかを考えることが大切だそうです。
罠3:「適応」の罠
人間は新しい環境や物に慣れてしまう「快楽適応」という性質を持っています。高価な買い物をしても、すぐに慣れてしまい、元の幸福度に戻ってしまうんですね。この「適応」を意識して、一時的な喜びではなく、長期的な満足につながる使い方を選ぶことが大切です。
私が実践している「幸せなお金の使い方」3つの例
友人との会話を経て、私自身も「お金の使い方」を少し見直してみました。ここ数ヶ月で実践してみて、確かに幸福度が上がったと感じる使い方を3つ紹介します。
例1:定期的な「経験への投資日」を設ける
毎月第2土曜日を「新しいことにチャレンジする日」と決めて、予算3,000円で何か新しい経験をするようにしています。先月は初めての陶芸体験、今月は天体観測ツアーに参加しました。新しい発見や学びがあり、日常に変化をもたらしてくれる小さな投資です。
例2:「時間を買う」ための支出を増やす
以前は「自分でやるべき」と思っていた家事の一部を外注するようにしました。具体的には、2週間に一度の大掃除をハウスクリーニングサービスにお願いするようにしたんです。費用は月に約1万円増えましたが、その分の時間で副業を始めることができ、結果的には収支もプラスに。何より掃除のストレスから解放された心の余裕は、お金以上の価値がありました。
例3:「人との時間」に優先的にお金を使う
家族や親しい友人との時間を大切にするために、少し予算を増やしました。例えば、両親を月に一度は少し良いレストランに招待する、友人の誕生日には心のこもった贈り物をする、という具合に。関係性が深まり、お互いの幸福感が高まっていくのを実感しています。
「幸せなお金の使い方」を習慣にするコツ
最後に、友人が教えてくれた「幸せなお金の使い方」を習慣にするためのコツをシェアします。
コツ1:「価値観」を明確にする
自分にとって本当に大切なものは何か、どんな生活が理想か、老後どうありたいかなど、自分の価値観を書き出してみる。そうすればお金の使い方に「軸」が生まれ、迷いが減るそうです。
友人の助けを借りて私も書き出してみました。すると「新しい経験を通じて成長すること」「家族や友人との良質な時間」「心身の健康」が自分にとっての3大価値観だとわかり、お金の使い方の優先順位が明確になりました。
コツ2:「感謝日記」をつける
心理学研究では、日々の小さな幸せに感謝する習慣が幸福度を高めることがわかっています。友人のアドバイスで、「お金を使って良かったこと日記」を始めました。「このお金の使い方で得られた幸せ」を書き留めることで、自分にとっての「価値ある支出」のパターンが見えてきて面白いです。
コツ3:定期的に「支出の棚卸し」をする
3ヶ月に一度、すべての支出を「幸福度向上に貢献しているか」という視点で見直します。「習慣になっている支出」こそ、実は見直す価値があるのだそうです。
例えば、私は長年続けていた雑誌の定期購読を見直し、ほとんど読まないまま積ん読になっていることに気づきました。その分のお金を、実際に行きたかった展覧会の年間パスに振り替えたところ、明らかに生活の質が向上しました。
まとめ:「お金と幸せ」の新しい方程式
友人との会話と、その後の実践から学んだ「お金と幸せ」の関係をまとめると:
- お金で幸せは買える。ただし「使い方」が重要
- 「モノ」より「経験」にお金を使う方が長期的な幸福度が高い
- 日々のストレスを減らす支出は、生活の質を大きく向上させる
- 「時間を買う」発想で、有限な人生の価値を高められる
- 「すぐに手に入れる」より「少し待つ」方が満足度が上がる
- 人との関係性を深める支出は、幸福度への投資効果が高い
- 「比較」「ステータス」「適応」の3つの罠に気をつける
- 自分の価値観に合った支出かどうかを定期的に見直す
結局のところ、「お金の金額」ではなく「お金との関係性」こそが、私たちの幸福度を左右しているのだと思います。
友人が最後に言った言葉が印象的でした。「お金は目的ではなく、あなたの大切な価値観を実現するための道具。その道具を効果的に使えば、確かに幸せは買えるわよ」
皆さんも、今日から少しだけ「お金の使い方」を意識してみませんか?小さな変化が、大きな幸福につながるかもしれません。
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。皆さんの「お金との付き合い方」が、より幸せなものになりますように。
また次回のブログでお会いしましょう!
お金屋より